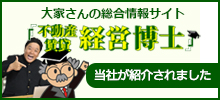業界ニュース
-
2025年4月 賃貸業界ニュースから
2024年の住宅着工統計がリーマンショック以来の80万戸割れ
2024年の新設住宅着工戸数は持家、貸家、分譲マンションを合わせた全体で約79万戸となり、リーマンショック以来15年ぶりに80万戸を下回りました。
このうち貸家(賃貸住宅)の着工戸数は34万2,044戸(前年比0.5%減)、着工床面積は16,098千㎡(同2.3%減)と2年連続の減少となりました。
次に各地域の貸家着工戸数を元にトレンドを見ていきます。
地域別では、首都圏で東京都が65,433戸(前年比6.9%減)と減少する一方、千葉県(19,411戸、同12.0%増)、神奈川県(27,044戸、同6.9%増)、埼玉県(20,258戸、同5.3%増)と周辺県が好調です。
関東圏の賃貸仲介業者によると、「分譲マンション価格の高騰により住宅購入を断念した層が賃貸市場に流入し、特にファミリー向け賃貸住宅の需要が増加している」とのことです。
この需要増加を背景に、都内のある管理会社の調査では、2023年12月時点での東京23区内の募集家賃が2020年比で平均13%も上昇していることが明らかになっています。
POINT1 建築費の高騰が住宅着工数減少の主因に
住宅着工数の減少は建築費の高騰が大きな要因とみられます。
木造住宅の建築費はコロナ前と比べて15.1%上昇し、建設業の就業者数は1997年の685万人から2024年には485万人まで減少。国が定める2024年度の建設労務単価は前年度比5%超の賃上げが予定されており、このような建築費高騰が続けば、ますます「建て控え」が増加しそうです。
また、中期的なトレンドにおいても日本の住宅市場は大きな転換点を迎えています。
POINT 2 世帯数減少と単身世帯の増加が進行
2023年を境に世帯数は減少に転じ、2040年までに5%程度減少する見通しです。特に単身世帯が全体の4割近くまで増える一方、「夫婦と子供」世帯は2割程度まで減少する予測です。こうした人口動態の変化を背景に、2025年以降も着工数の減少が継続すると予想されます。
全体で単身世帯が増加する中、コンパクトで機能的な物件への需要が高まるとみられます。特に都市部では、在宅勤務対応の設備(作業スペース、高速通信環境)を備えた物件の人気が増すでしょう。
また人口流入が続く首都圏周辺県や大阪、京都などの大都市、半導体産業が集積する熊本や観光需要が高く世帯数の増加が続く沖縄など、特定の成長分野を抱える地域では今後も賃貸需要が堅調に推移する一方、人口減少が著しい地方では空室率の上昇と家賃の下落圧力が強まることが予想されます。
POINT 3 入居者ニーズを捉えた戦略的投資が鍵に
こうした構造的な変化の中、これまで以上に入居者の好みを重視した戦略的な投資が重要になりそうです。
ある調査では、省エネ基準を満たす物件は入居率が平均8%以上高くなるというデータもあります。燃料費の高騰を受けて年々重くなる光熱費負担に敏感な入居者はますます増加しそうです。こうした動きを意識しながら、補助金制度を活用したリノベーションなどを念頭に物件の価値向上が求められるでしょう。
これからの賃貸住宅経営は、地域の特性を踏まえ、入居者のニーズを抑えた投資判断がこれまで以上に重要となるのは間違いなさそうです。